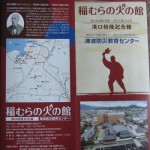8月28日に脳梗塞を発症して入院。その後退院して2か月余、再発がないよう毎日欠かさず薬を飲み、水を呑み、ウォーキングをし、食事は魚野菜中心の減塩食事。アルコールは全くた呑まない。といった毎日である。おかげさまで軽症であったので、ふら付きはあるものの以前の様に歩ける。自転車に挑戦したところ全く違和感なく乗れたの郵便局などは自転車で行っている。自動車運転は自動車学校の先生に横に乗ってもらって技量を見てもらったところマルであったので、駅までたまに家族の送り迎えを行なっていた。
このような単調な日常を送っている時、奈良県西吉野の柿博物館へ行こうと云う話が出た。いつでも運転を交代できる様に妻に横に乗ってもらい意を決して行ってみた。片道約1時間、結果は何事もなくいってくることができました。 国道310号を河内長野から金剛トンネルを通って五條へ。さらにそのまま吉野川を「越して南へ数キロ。やがて柿博物館への案内がありそれに従って行くと苦も無く到着。明日23日は柿祭りとかでいろいろ準備していたが博物館見学には支障がなかった。
中にはいろん種類の柿の実の実物が展示されていた。後でちかくで作業をしている方に聞くと全国に約7000種類もあると聞き驚いた。 また、昔から柿から取れる柿渋で防水紙とか渋うちわとか、染物等が展示されていた。
この博物館の近くに柿の共同選果場があり、選外品は一般販売していることを知りそこへ行くこととした。数分で到着。既に多くの車が来て直販所は大変賑わっていた。正式に箱詰めされたものから、選外だが十分販売に耐えられるものまでいろいろあった。選外だが程度の傷の有無、熟し過ぎ、虫喰いや変形の違いによって、キロ当たり100円~300円までいろいろ。わが家と2階の息子一家用に選外品を手に入れて帰ってきた。自分で無事帰ってこられたことから、少しは行動範囲を広げても良いのかなと、明るい気分です。

マンションイベントでのオーナメントづくり

マンションイベントでのオーナメントづくり

マンションイベントでのオーナメントづくり

マンションイベントでのオーナメントづくり

マンションイベントでのオーナメントづくり
今日は、友達が、柿を下さいました。今の時季は、みかんとか、柿が、美味しいですよね。

遊びでつくったリプラグマステッカーが、mooから届いた
●先日、ある会合で「稲むらの火の館」(和歌山県広川町)を見学する機会がありました。特産の「温州みかん」の畑と、山頂までのびるオレンジ色や緑の山々に囲まれた町に、ひときわ目立つ3階建ての館があります。館内のガイダンスルームで、職員の方による説明がありました。 ①1854年(安政元年)11月「安政南海地震」の時、帰郷していた濱口梧陵(本家ヤマサ醤油)が「稲むら」(ススキという稲束を重ねたもの)に火を放って村人を誘導、多くの人を助けたこと。②被災から3ヵ月後には、私財を投じて家を建て、堤防建設の為に村人を雇ったこと。③3年後にはその堤防を完成させたという。
●「3D津波映像シアター」では、津波の恐ろしさと高台への避難の重要性を実感できます。地震から大津波が来るまでの状況が、中継画面のように写されます。又、「濱口梧陵」の物語を3Dによる迫力ある映像で繰り広げます。
●館より海岸に3分位歩くと「国史跡・広村堤防」があります。高さ5m長さ600mの堤防は松林がうっそうと繁っていました。昭和南海地震(昭和21年)の津波から護ったという。近くには、地震計付津波警報スピーカー(風力と太陽光発電・蓄電付)が設置されていました。また防潮堤も遠隔操作で閉じる様になっているとのこと。 防災の先進的な取り組みに、大変勉強になりました。