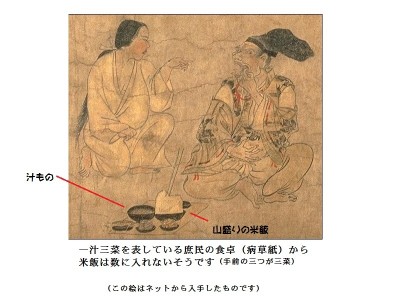◆「いきいき堺市民大学」卒業生の集い(第4月会)で今月はお友達が活動している堺市民合唱団の第49回定期演奏会がソフィア・堺での開催があり、みんなで激励を兼ねて行って来ました。
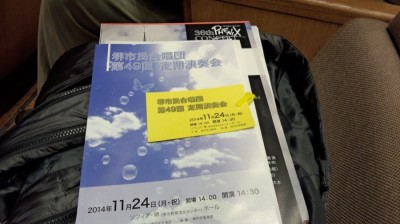
◆合唱や音楽には素養がないのですが、最初は馴染のある曲からはじまり、最後のアンコールも話題性のある曲目で楽しい時間を過ごさせてもらいました。

◆今回のプログラムは
第1ステージ 関白宣言
第2ステージ めいどいんNHK
休 憩
第3ステージ 混声合唱組曲・黙礼
最後にアンコール3曲の熱唱でした
空・道・河
いのちの歌
海(松原遠く消ゆるところ)会場の皆さんも一緒になって大合唱

◆会場を去るときは団員さんの合唱で送ってもらうと共に、第4月会の有志でお友達に感謝の花束を贈って後にしました。 管弦楽の演奏は何度か行った事はあったのですが、合唱もいいな~ぁと感じた。
ひとり言
演奏会での撮影は難しく拍手で団員を迎える時や各ステージ演奏の終了時に拍手に紛れてシャッターを切りました。なか々撮影ができる雰囲気ムードでは無い事を実感した(撮影に関して主催者に確認したのですが快諾とは行かなかったのですがわからないようにやってもらえれば・・・・でした)。



 牛滝温泉公園
牛滝温泉公園