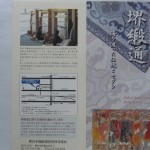●「第2回愉快・爽快・空海ウォーク」の中で、「紀州街道」沿いには現在の堺の産業基盤に大きく寄与したものがありました。 その一つは「堺刃物伝統産業会館」で展示・販売されている「堺打刃物」です。 「16世紀ポルトガルよりタバコが伝わり、・・タバコの葉を刻む『タバコ包丁』が堺で初めてつくられた」(当会館パンフ)という。古墳時代の鍛冶技術が生かされ、現在ではプロ用包丁のほとんどが、堺で生産されているといわれています。
●国の重要文化財の「山口住宅」(堺市立町屋歴史館)は、江戸時代前期の町屋例として極めて貴重な民家という。 その住宅の和室の一室に「堺緞通」のミニ耕織機が展示されていました。1831年藤本荘太郎が鍋島緞通や中国製を模して、泉利兵衛に作らせ売り出したのが始まりとのこと。ピーク時(1831年)には年間89万畳を生産していたという。昭和30年代以降はマットやカーペットなどの敷物産業へと引き継がれました(堺式手織緞通技術保存協会パンフ)。大阪府指定無形民俗文化財として技術・保存をはかっています。
●“ウォーク”のゴールは堺市役所の展望ロビーです。ロビーでは「堺鉄砲」の展示コーナーがありました。日本に鉄砲が伝わり、鋳物師や鍛冶の集住地である堺で、製造されるようになったという(博物館パンフ)。江戸時代には装飾性の高い堺鉄砲がつくられたとのこと。その技術(砲身)が自転車のハンドルに生かされ、自転車生産へと発展していったと言われています。 観光ボランティアのakj さんより説明を聞きました。ありがとうございました。