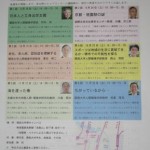●10月2日(日)堺市南区区民まちづくり会議による「こおどり・秋めぐりツァー」がありました。爽やかな秋空の下、約40名の参加者が南区役所~西山城跡~桜井神社~上神谷田園地区~法道寺~コスモス館までのツァーを楽しみました。道中、郷土史家・桧本多加三氏よりそれぞれの歴史や文化を解り易く説明していただきました。 桜井神社の「こおどり」は無形民俗文化財であること。雨乞いの(火祭)をして「雨を乞う踊り」、鬼神が背負ってるかんこを子供に見立てた「子おどり」とか、踊り手が「鼓を持って踊る」ことから・・等の説があるという。
●「こおどり」の奉納前には、宮入の上神谷(にわだに)連合(片蔵・豊田・栂・釜室・泉田中)の5基のだんじりが勢ぞろいしていました。桧本氏の説明によれば、堺型(上だんじり)と岸和田型(下だんじり)があるという。岸和田型はスピードとやり回しのため屋根が平らで車輪幅が広く、堺型はその反対で、やり回しではなく、だんじりを前輪と後輪を交互に持ち上げるという。南区で堺型は泉田中・大庭寺・大森だけになったとのこと。
●上神谷小学校前では田圃の稲が黄金色に実っていました。昨年も同時期に投稿しましたが、何回来てもこの田園風景には、日本の原風景を見るようで、心和みます。今日は金剛山などがくっきりと望むことが出来ました。