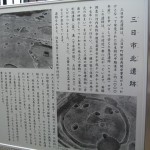●南海高野線・千早口駅近くで昼食を済ませた後、紀見峠越えをめざす。千早口集落をぬけ、松明屋(弘法大師が高野山を開く為に立ち寄ったところとのこと)から、再び廃線の“なんてんの道”を上がってゆく。途中「七里石」のある国道を眺めたり、天見小学校~南天苑の説明を聞く。天見駅で小休止のち国道371号線・歩道を進む。
●正面の高い峰の上が紀見峠である。ウォークの参加者は黙々としっかりとした歩調で上がってゆく。対面二車線の旧国道のつづら折の道を何回か繰り返す。山あいには「マタタビ」の木が、白いまだらの葉で一面に繁っていた。 やがて、山の稜線が切れ、空が明るく広がっている所に出た。「紀見峠」(標高400m)である。
●峠には「六里石」の石柱が立っていた。昔は「紀伊見峠」と言われ、「番所」や「旅籠」が置かれていたとのこと。また、数学者・岡潔博士(1901年~1978年)は幼少時代をこの地で過ごしたという。明治期には70戸あった集落も、現在は20戸足らずの静かな集落となっているとのこと。
●峠の集落を抜け、雑木林の森の急な山道を下りきると、紀伊・高野山の山並みが見渡せる場所に出てきた。雲で全容は望めないが、峠を越えた実感が沸いてきた。終着地の紀見峠駅もあと僅かである。