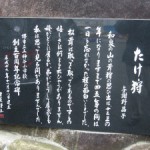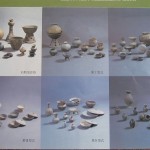●今年もあと2日。ブログを始めて一年経ちました。印象に残った町かどの風景をあげてみました。
そのひとつは、上神谷小学校にある与謝野晶子「たけ狩」の文学碑と田園風景をあげたいと思います。大正時代の泉北丘陵の風景が想い浮かんできます。 「松茸狩り」に夢中になれるほどの松林と里山に復活させてみたいものです。
(2)「いきいき堺市民大学」での受講も意義深いものがありました。「新しい公共」、NPOによるボランティア活動、「堺の歴史」、「堺の経済活性化」等々多種多様な分野で活躍している方々の講義を直接聞けたことでした。
(3)また「三朝温泉残照」記事の木下利玄の歌碑でした。三朝川のたもとにひっそりと、幾分苔むした岩石に、歌が刻まれていました。当時の温泉の情景が歌に表れていました。
●その他にも、ブログに投稿した記事には、一つひとつ町かどの風景として印象に残っています。この機会を与えていただいた関係者の方々に感謝したいと思います。ブログカフェに集まった仲間たち、また閲覧していただいた皆さんに感謝申し上げます。みなさん、よいお正月をお迎えください。 \(^0^)/~~