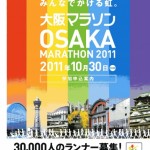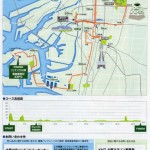大阪場所の稽古場見学のこと、大相撲出羽の海部屋の大阪場所の宿舎として祥雲寺であることを知った。そして午前6時から10時ごろまで朝稽古をやっているとも聞いた。翌日、物は試しと少し遅くなりましが見学に出かけた。到着したのは9時30分ごろであったが、土俵の中では白鵬関が若い者に稽古を付けている最中であった。そして土俵の周りには30人程の力士が、一番が終われば、次は自分と手ぐすね引て待っている。身体がぶつかる音、荒い息づかい、叱咤の声、激励の声等、TVで見る相撲とは全く異なり、厳しさも伝わってくる。しばらくして白鵬関と数名の力士が出て行った。
実は白鵬関の宮城野部屋は宿院頓宮が稽古場だそうで、そちらへ帰って行ったのだそうだ。今、出羽の海部屋はいわる関取が居ないので出稽古で稽古をつけてやりに来ていたようです。白鵬関を見られたのは全くラッキーなめぐり合わせであった。朝稽古は例年ならば、放駒部屋は八田北自治会館、陸奥部屋は出雲大社大阪分祀、追手風部屋は百舌鳥八幡宮、春日山部屋は東光学園、白鵬の宮城野部屋は頓宮、等で見学できた様ですが、昨年の大阪場所がなかったので今年はどうでしょうか。1年に1回のチャンスですから、少し早起きして見学に出かけてみてはいかがでしょう。 (写真の上に矢印を移動させて、矢印が手の形に変わると、クリックすると大きい写真が表示されますよ。)